これまで、つみたてNISAを活用してコツコツとインデックス投資を続けてきた方の中には、次のような疑問や不安を感じ始めている方も多いのではないでしょうか。
- このままずっと積立だけでいいのかな?
- 老後までに必要な資産がちゃんとつくれるだろうか?
- 投資からの「現金収入」もそろそろ得たい…
つみたてNISAは、少額から始められて、長期的な資産形成に向いている王道の投資手法です。
「長期・積立・分散」という安定運用を基本にしているため、投資初心者でも失敗しにくく、着実に資産を育てることができるというメリットがあります。
ただし、つみたてNISAだけでは、「配当金」などの定期的な現金収入(インカムゲイン)を得ることが難しいのも事実です。
そこで注目したいのが、新NISAの「成長投資枠」を活用した高配当ETF投資です。
特におすすめなのが、まずは「月1,000円の配当収入」を目安とした少額からの高配当ETF戦略。
インカムゲインと将来の資産成長をバランスよく狙える方法として、つみたてNISAの次のステップとしても非常に有効です。
ETF(上場投資信託)は、複数の銘柄に分散して投資できるため、個別株よりもリスクを抑えやすく、初心者でも比較的取り組みやすいのが魅力です。
中でも「高配当ETF」は、毎年安定した配当金を得られる可能性が高く、配当による現金収入を得たい方にピッタリの投資先です。
本記事では、以下のような疑問を持つ方に向けて、実際におすすめのETF銘柄も交えながら、「月1,000円配当」を目指す投資戦略を丁寧に解説していきます。
- なぜ今、成長投資枠で高配当ETFを選ぶ人が増えているのか?
- 月1,000円の配当を得るには、どれくらいの資金が必要?
- 初心者にも扱いやすい高配当ETFって、どれを選べばいい?
これから「資産を積み上げるだけ」の投資から一歩進んで、配当金というかたちでお金を受け取るステージに進みたい方は、ぜひこの記事を最後までご覧ください。
結論|月1,000円の配当収入を目指すなら、高配当ETF×成長投資枠の活用が効果的
つみたてNISAによるインデックス投資で「資産を増やす仕組み」を構築してきた方にとって、次のステップとなるのが「資産から現金収入を得る」戦略です。
その選択肢として有効なのが、新NISAの成長投資枠を活用した高配当ETF投資です。
成長投資枠では、個別株やETFなどの自由度の高い商品に対して、非課税で投資が可能です。この枠をうまく使うことで、インカムゲイン(配当収入)+キャピタルゲイン(値上がり益)の両方を狙える運用スタイルが実現します。
特に、高配当ETFは複数の銘柄に分散投資された商品であり、個別株よりもリスクを抑えながら、安定した配当を受け取りやすいのが特徴です。
「お金を育てる」から「お金が生み出す」フェーズへ。
この感覚を得られることが、ETF投資の大きな魅力です。
月1,000円の配当を得るには、いくら投資が必要?
たとえば、配当利回り4%のETFに投資する場合、年間12,000円(=月平均1,000円)の配当収入を得るためには、以下のような計算になります。
- 年間配当:12,000円
- 利回り:4%
- 必要投資額:12,000円 ÷ 0.04 = 30万円
このように、目標とする配当額から逆算して投資金額を考えることで、無理のない資産形成の設計がしやすくなります。
月1,000円という金額は決して大きくはありませんが、「現金を受け取る実感」を得るには十分なインパクトがあります。そこから少しずつ配当額を増やしていく、その第一歩として最適なのが、成長投資枠を活用した高配当ETFの導入なのです。
なぜ、高配当ETF×成長投資枠が初心者におすすめなのか?
つみたてNISAを活用したインデックス投資は、「資産形成の王道」として多くの投資初心者から支持を集めています。
実際、「長期・積立・分散」というシンプルな仕組みは、投資経験が少ない方でも取り組みやすく、将来の資産づくりにおいて非常に優れた土台となる方法です。
しかし、そんなつみたてNISAにも一つ弱点があります。
それは「配当金」などの定期的な現金収入(=インカムゲイン)が得られないという点です。
つみたてNISAの非課税枠は、あくまで投資信託による値上がり益(キャピタルゲイン)を重視した仕組みです。そのため、投資先となるファンドの多くが配当金を出さず、分配金も極力抑える運用方針を取っています。
結果として、「資産は増えるけど、お金は手元に入ってこない」状態が長く続くのです。
この弱点を補いながら、もう一段階上の資産形成を目指せる方法として注目したいのが、新NISAの「成長投資枠」を活用した高配当ETF投資です。
成長投資枠なら非課税で「インカムゲイン+キャピタルゲイン」の両取りが可能
成長投資枠では、つみたてNISAと違い、ETFや個別株といった幅広い商品に非課税で投資できるのが最大の特徴です。
これにより、資産形成のスタイルにも自由度が生まれ、「増やす」と「受け取る」のバランスを自分で設計できるようになります。
なかでも高配当ETFは、インカムゲイン(配当収入)とキャピタルゲイン(値上がり益)の両方が狙えるため、初心者にとっても非常に魅力的な選択肢です。
例えば、月1,000円の配当収入を目標に、安定した利回りが見込めるETFを少しずつ積み立てていく戦略なら、つみたてNISAと並行して「資産を増やす+現金収入を得る」のハイブリッド運用が実現します。
これから先のライフスタイルやライフステージに応じた選択肢を広げておくうえでも非常に重要なアプローチです。
ETFなら分散投資でリスクを抑えつつ、安定収益も期待できる
「高配当株=リスクが高そう」と思われがちですが、ETFを活用することで、分散効果によってリスクを抑えた投資が可能になります。
例えば、個別株であれば、業績悪化や減配によるリスクを1社で背負ってしまう可能性があります。
しかし、ETFであれば複数の銘柄に分散されているため、一部の企業に問題があっても全体のリターンが大きく崩れるリスクは少ないのです。
さらに、高配当ETFの中には金融・インフラ・不動産・エネルギーといった安定セクターが多く含まれており、経済変動の影響を受けにくいという特性もあります。
また、毎年一定の配当を受け取れることで、相場が軟調な局面でも精神的な安心感が得られるのもETF投資の大きなメリットです。
投資初心者こそ、「守りながら攻める」ポートフォリオとしてETFを活用すべきタイミングです。
日本株・米国株の高配当ETF それぞれのメリットとは?
高配当ETFを活用した配当収入戦略を考えるうえで、日本株と米国株のどちらを選ぶべきか悩む方も多いかもしれません。
実は、それぞれに異なる強みがあり、両方をバランスよく取り入れることが、より安定した資産形成につながります。
日本株ETFの魅力|安定配当と堅実経営で守りを固める
日本企業は近年、株主還元に積極的な姿勢を見せるようになっています。
東京証券取引所による「PBR(株価純資産倍率)1倍割れ」企業への改善要請や、企業経営のグローバル化を背景に、配当性向の引き上げが進んでいるのです。
その結果、以下のような特徴をもつ日本株ETFが増えてきました。
- 景気変動に強く、減配リスクの低い堅実企業が多い
- 内部留保が豊富で、財務基盤が安定している
- 国内中心のビジネスモデルで為替リスクが少ない
たとえば、電力・通信・不動産・金融などのセクターを中心に、安定した配当を継続している企業を多く組み込んだETFは、日本株ならではの「守りの資産」として活用できます。
米国株ETFの魅力|配当水準が高く、増配実績も抜群
一方、米国の高配当ETFは攻めの配当戦略に最適な選択肢です。
米国企業は長年にわたり、配当の安定性と増配に対する強い文化を築いてきました。
たとえば、以下のような特徴が米国高配当ETFの魅力です。
- 利回り3〜4%台でも、安定して増配が続いている企業が多い
- 世界的に競争力のある大型企業を多数含む
- 世界の市場で信頼を集める連続増配企業が厳選されている
また、米国ETFは取引量が多く、管理費用(=ETFの運用にかかる年間コスト)が低いのも特徴です。長期投資でもムダなコストを抑えられるため、資産形成の効率を高めることができます。
2つのETFを組み合わせることで「守り」と「攻め」が両立できる
日本株ETFと米国株ETF、それぞれの特徴を理解したうえで組み合わせれば、投資先の国を分けてリスクを分散しながら、通貨や業種のバランスも整えることができます。
- 日本株ETF → 為替リスクがなく、安定志向で守りを固める
- 米国株ETF → 世界成長の恩恵を受けつつ、配当も得る攻めの要素
たとえば、「月1,000円配当」を目指す場合も、米国ETF中心で配当水準を高めつつ、日本ETFで安定性を補強するといった組み合わせは非常に有効です。
つまり、これから高配当ETFを活用するなら、「日本か米国か」ではなく、日本も米国も取り入れていく姿勢が大切です。
どちらか一方に偏るのではなく、自分のリスク許容度や資産配分に合わせてバランスを取りながら、配当収入のある暮らしを目指していきましょう。
月1,000円の配当を目指すなら?初心者向けおすすめ高配当ETF5選【配当月も解説】
ここからは、成長投資枠を活用して「月1,000円の配当収入」を目指す方におすすめの高配当ETF5選をご紹介します。
今回は「分配月(配当月)」の情報も明記していますので、実際にどのタイミングで配当が入るのかもイメージしやすくなっています。
① SPDR ポートフォリオS&P500 高配当株式ETF(SPYD)
| 株価(1口あたり) | 分配金利回り | 年間配当(概算) | 分配月 |
|---|---|---|---|
| 約6,126円 | 約4.53% | 約280円/口 | 3・6・9・12月 |
特徴とおすすめポイント
SPYDは、米国の代表的な株価指数「S&P500」の構成銘柄のうち、配当利回りの高い上位80社を対象にした高配当ETFです。
セクターごとの偏りを抑える設計になっており、金融・不動産・エネルギー・公益など幅広い業種に分散投資されているのが大きな魅力です。
また、四半期ごと(年4回)に安定した分配金を受け取れる仕組みのため、「お金が入ってくる感覚」を得やすいのもインカム投資としてうれしいポイントです。
他の米国ETFと比較しても、利回りの高さが際立つため、「配当金で生活の足しにしたい」という人にとっては、非常にバランスの良い選択肢と言えるでしょう。
株価もそこまで高額ではなく、少額からのスタートにも適しているため、初心者が成長投資枠での第一歩を踏み出すETFとして非常に人気があります。
こんな人におすすめ
- 少額から配当収入を実感したい人
- 高利回りかつ安定性のあるETFを探している人
- 四半期ごとの分配で定期収入の習慣を作りたい人
「インカムを実感しやすい1本」として、成長投資枠に最初に組み入れるETFとしてぴったりです。
② バンガード 米国高配当株式ETF(VYM)
| 株価(1口あたり) | 分配金利回り | 年間配当(概算) | 分配月 |
|---|---|---|---|
| 約18,891円 | 約2.84% | 約530円/口 | 3・6・9・12月 |
特徴とおすすめポイント
VYMは、米国の配当水準が安定している大型〜中型企業400社以上に分散投資できるETFです。生活必需品・金融・ヘルスケア・エネルギーなど、複数の業種に幅広く分散されており、個別銘柄の値動きに左右されにくいのが大きな特徴です。
また、長期的に安定配当を維持してきた企業が中心に構成されているため、「配当を得ながら資産をじっくり育てたい」という方にぴったりの運用設計です。
さらに、VYMは経費率がたったの0.06%と非常に低コストで運用できるため、長期投資においてコストの負担を最小限に抑えることができます。これは、何十年と積み立てるうえでは無視できない重要なポイントです。
配当は3・6・9・12月の四半期ごとに分配されるため、年4回のキャッシュフローも見込めます。配当水準はおおむね年利3%前後で推移しており、極端な値動きも少ないため、守りの資産形成にも適しています。
「利回り重視だけでなく、分散や安定性も重視したい」という方にとって、VYMは心強いパートナーとなってくれるでしょう。
こんな人におすすめ
- 安定的な配当と分散投資を両立させたい人
- 成長投資枠での長期・堅実な資産形成を目指す人
- コストを抑えて安心して保有したい初心者
- 米国株ETFを長期で積み立てたい人
「高配当ETFの基本形」として、誰にでも安心してすすめられる定番銘柄。
投資初心者の土台を支えてくれる、バランスの取れた1本です。
③ 楽天・シュワブ・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型)
| 株価(1口あたり) | 分配金利回り | 年間分配金(概算) | 分配月 |
|---|---|---|---|
| 約10,000円 | 約3.5〜4.0% | 約350〜400円/口 | 2・5・8・11月 |
特徴とおすすめポイント
「楽天・シュワブ・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型)」、通称「楽天・SCHD」は、米国の高配当株式に分散投資できる人気ファンドです。米国の代表的なETFである「SCHD(シュワブ・米国配当株式ETF)」に投資し、配当利回りと成長性のバランスを兼ね備えた運用が魅力です。
このファンドの特徴は、四半期ごと(年4回)に安定した分配金が得られる点です。2月・5月・8月・11月の年4回に分配があるため、「お金が入ってくる感覚」を得やすく、資産形成を楽しみながら続けられるのがポイントです。
投資対象となる「SCHD」は以下のような厳しい基準で構成銘柄を選定しています:
- 10年連続で配当を実施している米国企業
- 時価総額5億ドル以上
- 配当利回り・ROE・キャッシュフロー・配当成長率など複数の財務指標でスクリーニング
また、金融・エネルギー・生活必需品・ヘルスケア・情報技術など、幅広いセクターに分散投資されているため、リスクを抑えながら安定収入を得ることが可能です。
こんな人におすすめ
- 四半期ごとに分配金を受け取りたい人
- 米国高配当株に分散投資したい人
- 成長投資枠で安定した収入源をつくりたい人
- 低コストかつ長期運用に適したファンドを探している人
「楽天・SCHD」は、年4回のインカムゲインを実感できるETF型ファンドとして、成長投資枠での運用にぴったりです。信託報酬も年率0.1238%と低コストで、長期的な資産形成を目指す初心者にもおすすめです。
④ NF・日経高配当50 ETF(1489)
| 株価(1口あたり) | 分配金利回り | 年間配当(概算) | 分配月 |
|---|---|---|---|
| 約2,200円 | 約3.9%(過去5年平均) | 年間約87円/口 | 1・4・7・10月 |
特徴とおすすめポイント
「日経平均高配当株50指数」に連動するETFで、日経平均株価の構成銘柄の中から、予想配当利回りが高い上位50銘柄に分散投資します。
過去の分配金実績を見ても、2017年の32.74円から2024年には78円まで増加。2025年4月時点では、すでに過去最高水準の分配金を記録しており、高配当の魅力が際立っています。
また、年4回(1・4・7・10月)の定期的な分配で、安定的なキャッシュフローも得られるのが特長。信託報酬は年率0.308%と、国内ETFの中ではまずまずの水準です。
構成銘柄には、武田薬品、日本たばこ産業、ソフトバンク、日本製鉄、三菱UFJなど、日本を代表する高配当企業が並びます。銀行、保険、鉄鋼など、いわゆる「高配当セクター」への比重も高く、分散効果とインカム収入の両立が期待できます。
さらに、毎年6月末に指数の見直し・銘柄入れ替えが自動的に行われるため、個別株の分析・管理が不要で、初心者でも手軽に高配当投資を継続できます。
こんな人におすすめ
- 「国内株で手堅くインカム収入を得たい」と考えている人
- 為替リスクを避けつつ、高水準の分配金を目指したい人
- 分散+高配当+非課税のNISA運用を効率よく行いたい人
- 個別株を選ぶのが難しい初心者投資家
⑤ NF・J-REIT ETF(1343)
| 株価(1口あたり) | 分配金利回り | 年間配当(概算) | 分配月 |
|---|---|---|---|
| 約1,800円前後 | 約4.6% | 年間約83円/口 | 2・5・8・11月 |
※10口、18,000円前後から購入可能
特徴とおすすめポイント
このETFは、東京証券取引所に上場するREIT(不動産投資信託)に幅広く投資し、東証REIT指数に連動するよう設計された商品です。REITとは、不動産賃貸収入や売却益を投資家に分配する仕組みの投資信託で、オフィスビル、商業施設、物流倉庫、住宅などを対象としています。
特長は、日本全国のさまざまな不動産に分散投資しつつ、安定的な分配金を目指せることです。REITの分配金は家賃収入をベースとしており、景気に左右されにくい側面があるため、安定的なインカムゲインを得たい方には最適な選択肢です。
また、同じ指数に連動するETFの中でも、純資産総額が最大クラスで流動性も高いため、売買しやすく、安心して長期保有が可能です。
分配金の原資はREITが得る不動産賃料であるため、一般的な日本株と比べて分配金利回りが高い傾向にあります。実際、年間3.5〜4.5%程度の利回りが期待できる水準であり、NISAの非課税メリットと組み合わせれば、効率よく現金収入を得られます。
信託報酬(保有コスト)は年率0.1705%(税込)と低コスト。10口あたり18,000円前後から購入可能なので、少額からスタートできるのも魅力です。
リスクと注意点
一方で、不動産市況の変化には注意が必要です。オフィスや商業施設の空室率が上がれば賃料収入が減少し、分配金に影響が出る可能性があります。
また、REITは多くが借り入れを活用して不動産を保有しているため、金利の上昇によりコストが膨らむリスクも考慮する必要があります。
ただし、株や債券と異なる値動きをする資産であるため、ポートフォリオ全体の分散効果を高める役割としては非常に優秀です。
こんな人におすすめ
- 定期的に分配金(現金収入)を得たい方
- 株式とは異なる資産で分散投資をしたい方
- 少額から不動産投資の恩恵を受けたい方
- 成長投資枠で安定収入を狙いたい初心者
月1,000円(年間12,000円)を受け取るために必要な投資額【ETF比較表】
「高配当ETFにいくら投資すれば、月1,000円の不労所得が得られるのか?」
このような疑問を持つ方のために、年間12,000円(月1,000円相当)の分配金を得るにはどのくらいの投資が必要か、代表的なETFごとにシミュレーションしてみました。
配当利回りや株価をもとに、ざっくりとした目安を一覧表にまとめています。
| ETF名 | 株価 (1口) | 年間分配金 (1口あたり) | 必要口数 | 必要投資額 (概算) | 分配月 |
|---|---|---|---|---|---|
| SPDR S&P500 高配当ETF(SPYD) | 約6,126円 | 約280円 | 43口 | 約263,418円 | 3・6・9・12月 |
| バンガード 米国高配当ETF(VYM) | 約18,891円 | 約530円 | 23口 | 約434,493円 | 3・6・9・12月 |
| 楽天・シュワブ高配当ファンド | 約10,000円 | 約375円 | 32口 | 約320,000円 | 2・5・8・11月 |
| NF・日経高配当50 ETF(1489) | 約2,200円 | 約87円 | 139口 | 約305,800円 | 1・4・7・10月 |
| NF・J-REIT ETF(1343) | 約1,800円 | 約83円 | 145口 | 約261,000円 | 2・5・8・11月 |
上記はあくまで「月1,000円の不労所得」を得るための目安です。
もちろん、ETFによって分配時期や値動き、税制の影響も異なるため、単純に利回りだけで判断するのではなく、自分の投資スタイルやリスク許容度に応じて選ぶことが大切です。
「まずは月1,000円程度の配当から始めてみたい」という方は、少額からスタートしやすいSPYDやNF・日経高配当50 ETFが人気の選択肢です。
一方で、「より安定した企業群で長期運用したい」という方にはVYMや楽天・SCHDファンドが向いています。
まずは1口購入してみることをオススメまします。
まとめ|つみたてNISAの次は、成長投資枠で「月1,000円配当」を目指す戦略を
つみたてNISAでのインデックス投資は、将来に向けた資産形成の土台として非常に優れた手法です。長期・分散・積立によって、コツコツと資産を増やすベースができあがります。
しかし、それだけでは得られないのが「配当金」という目に見える収入=インカムゲインです。
たった月1,000円(年間12,000円)でも、「お金が働いてくれている感覚」や「生活の一部を自分の資産でまかなえている実感」が得られます。こうした感覚が、投資を楽しく、継続しやすいものにしてくれるのです。
そこで次に活用したいのが、新NISAの成長投資枠です。ここでは、高配当ETFなどの「インカム+値上がり益」が期待できる銘柄に非課税で投資することが可能です。配当収入と資産成長の両方を狙えるため、つみたてNISAでは補えなかった攻めの戦略を取り入れることができます。
高配当ETFの運用でやりがちなNG行動とその対策
高配当ETFは個別株よりも手軽に分散投資できる魅力的な商品ですが、「ETFだから安心」と思い込みすぎると、思わぬ落とし穴にはまることもあります。
以下は、高配当ETFを活用する際に避けたいNG行動です。
| NG行動 | なぜNGなのか? | 対策ポイント |
|---|---|---|
| 利回りだけで選ぶ | 高利回りのETFは、一時的な株価下落によって見かけの利回りが高くなっている場合があり、分配金の持続性が低いケースも。 | 分配金の「過去実績」や「構成銘柄の健全性」も必ずチェックする |
| 1銘柄のみに集中する | ETFでも構成銘柄が特定セクターに偏っていると、景気や政策の影響を受けやすく、リスク分散が不十分になる。 | 異なる種類(米国・日本・REITなど)や複数ETFを組み合わせて分散投資する |
| 購入後に放置してしまう | ETFは自動で運用されるが、分配金の増減や構成銘柄の変更など、定期的なチェックがないと想定外のリスクに気づけない。 | 年1回は分配実績やポートフォリオを確認し、リバランスの検討をする |
| 為替リスクを軽視する | 米国ETFは為替相場の影響を強く受けるため、円高局面では配当や評価額が目減りすることがある。 | 為替リスクを抑えたいなら国内ETFを一部組み入れるなど、通貨分散を意識する |
| 課税口座で運用してしまう | 配当金には20.315%の税金がかかるため、課税口座だと受取額が目減りする。 | 成長投資枠を活用すれば、分配金への課税が非課税となり、効率よく収益を受け取れる |
高配当ETFは「放っておけばいい」と思われがちですが、実際は適度なメンテナンスと正しい目利きがあってこそ、安定したインカム収入につながります。
「利回り」だけに目を奪われず、ETFの中身や運用スタイル、相性のよい組み合わせ(VYM+J-REITなど)を見ながら、無理なく続けられる配当戦略を構築していきましょう。
高配当ETFの運用を始めるなら「楽天証券」がおすすめ
高配当ETFを成長投資枠で運用する際には、使いやすい証券口座の選択も重要です。初心者の方にとって、わかりやすく、日常生活に馴染みやすい口座が安心材料になります。
中でもおすすめは、楽天証券です。以下のような理由で、多くの初心者に選ばれています。
| 特徴 | 理由 |
|---|---|
| 楽天ポイントで投資できる | 日常の買い物で貯めたポイントをそのまま投資に活用でき、気軽に始められます。 |
| アプリが使いやすい | 初心者でも迷わない、シンプルな操作性。スマホ一つで投資管理が完結。 |
| 楽天キャッシュ積立ができる | 還元率最大0.5%の積立設定が可能で、長期運用のコストも実質的に抑えられます。 |
| つみたてNISAとの併用がしやすい | 成長投資枠と併せて、NISAを一本化して管理できるのも便利です。 |
楽天証券なら、配当金の受け取り履歴や残高推移も一目で確認できるので、「長期で配当生活をめざす人」にぴったりの環境が整っています。
まずは「月1,000円の配当収入」を目指してみませんか?
資産形成において「時間を味方につけること」はとても重要です。だからこそ、配当戦略も「早く・小さく・続ける」ことが大切です。
たった月1,000円からでも、配当収入を実感することでモチベーションが上がり、「もう少し増やしてみようかな」と前向きに資産を積み上げられるようになります。
つみたてNISAでの土台を築いたあと、次のステージとして「配当戦略」を取り入れることは、お金との付き合い方をより豊かにしてくれる一歩になるはずです。
まずは少額からでも始めて、ライフスタイルに合った自分年金を育てていきましょう。
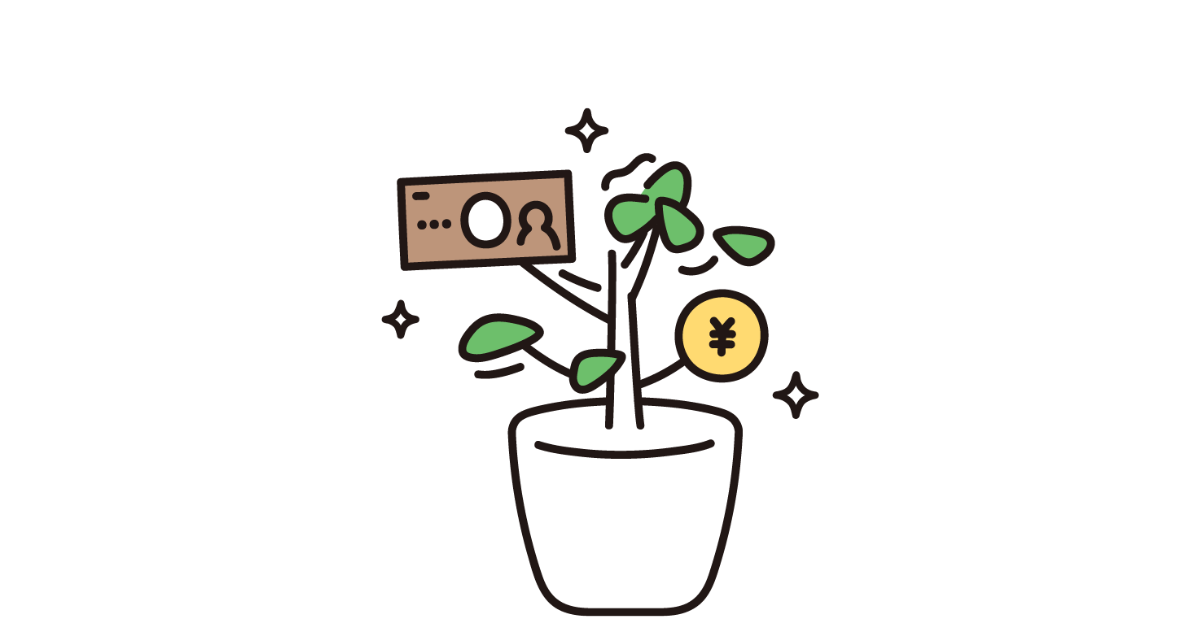

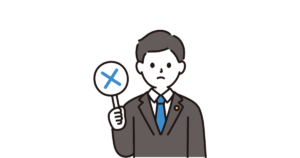


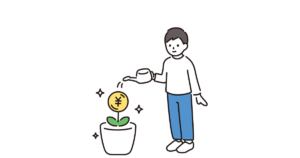
コメント